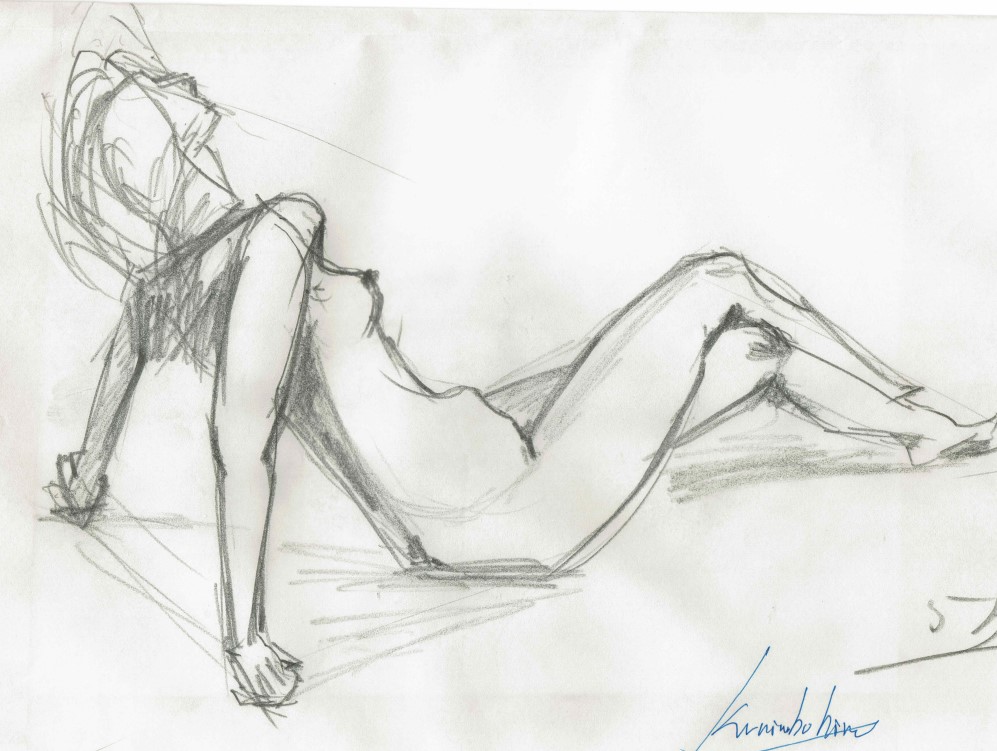量子もつれは、本当に重要な仕掛けであり、存在の根幹を支えている原理なのだと、つくづく、感じている。つくづく。
光子が粒と波の両方の性質を併せ持つように、量子が基本定数の整数倍のポジションしかとれないように、量子もつれは、ほとんど「公理」というべき、世界の基本的な原理なのだと思っている。
たとえば。光子でも電子でもいいが、何かの素粒子αがあったとする。
その素粒子αは、たとえば銀河系のま、私たちの恒星である「太陽」から発せられているとする。
太陽で放出された素粒子αが、地球で観測された素粒子αと「同一」であるということを保証するために、量子もつれがあるのだと、私は考えている。
すぎた時間にかかわらず、移動した空間にかかわらず、素粒子αが、「同一」のものであるということを保証する仕掛けとして、量子もつれを理解する必要がある。
もし、量子もつれという現象がなかったとしたら、太陽で発射された素粒子αと、観測された素粒子αが「同一」であることを証明することはできない。
逆に、どんなに遠く離れていても、どんなに時間が経っていても、量子もつれという現象が確認されるなら、それは「瞬時」に情報を好感することができる。
時空特性によらない、独立した存在の「ペア」となっている。
実は、ペアと思えるのは観測者の視点であり、私の解釈によれば、「もともと同じ素粒子αを、別な手段で観測したにすぎない」ということになる。
同じ素粒子αを観測したのだから、素粒子αの渋滞を変えれば、遠く離れた「ペアの素粒子」に粒子もつれの現象が起こるのは、何の不思議も理屈もない。
だって「同じ」素粒子αなのだから。
わからない人には、今、私が描いていることが発見であることを認識できない。それでいいと私は思う。
でも10年後、量子コンピュータがそれなりの成果を上げられるまで成長したころに「あれ、こいつの言っていること、当たったな」とわかることになるはず。
そんなことを考えて、眠りにつく日々もまた、楽しい。